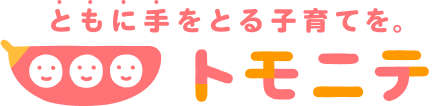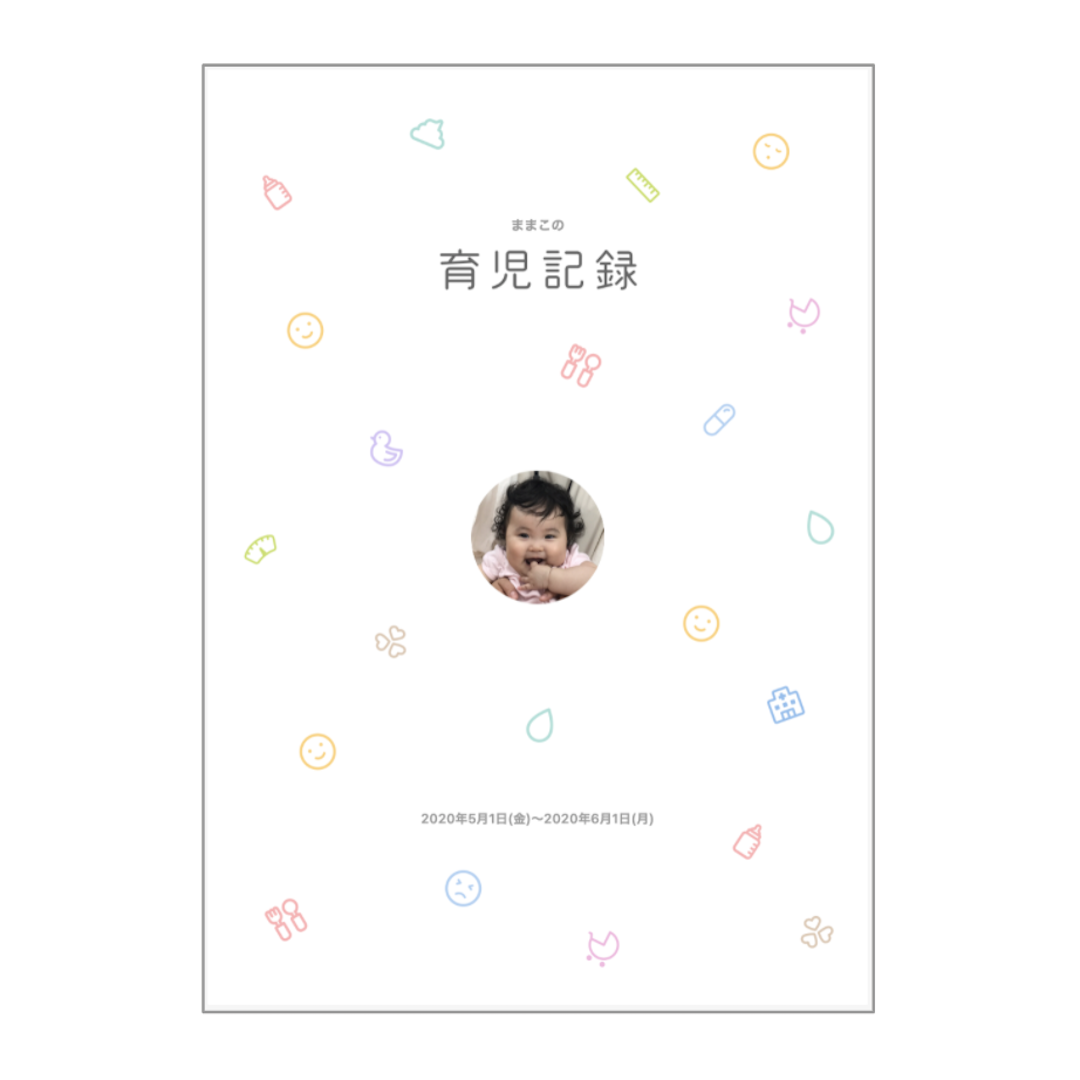【管理栄養士監修】離乳食の昆布だしはいつから?作り方とおすすめレシピ
アミノ酸系の旨味成分であるグルタミン酸を多く含み、素材のおいしさを引き出すのに欠かせません。
今回は、離乳食の昆布だしはいつから与えられるのか、下ごしらえのコツやおすすめのレシピをご紹介します。
アミノ酸系の旨味成分であるグルタミン酸を多く含み、素材のおいしさを引き出すのに欠かせません。
今回は、離乳食の昆布だしはいつから与えられるのか、下ごしらえのコツやおすすめのレシピをご紹介します。
離乳食に昆布だしはいつから使える?
昆布だしはゴックン期・離乳初期(生後5~6ヶ月頃)からOK。薄めて少量を使用して
昆布だしは、ゴックン期・離乳初期(生後5〜6ヶ月頃)から与えることができます。
料理を作るときにだし汁を加えて旨味をプラスします。料理の和風、洋風にこだわらず、利用してみましょう。
離乳食は基本的に素材の味を大切にし、塩分を含む調味料は多く使用しません。
赤ちゃんがなかなか食べてくれないとき、昆布だしで料理の旨味をアップしてあげれば喜んで食べてくれるかもしれませんね。
昆布だしは離乳初期から与えても問題ありませんが、ヨウ素の1日摂取量の関係で、使用量に目安があります。
大人の昆布だしを使用する場合は薄めて少量を使用しましょう。
また摂りすぎを防ぐためにも、昆布だしに限定せず、初期は野菜だし、次にかつおだしなども使用していきましょう。
どのくらいの量を与えたらよい?
大人用の昆布だしから使用する場合は、ヨウ素の濃度が濃いため、必ず5~10倍に薄めます。
ヨウ素は、海藻類、特に昆布に高い濃度で含まれています。赤ちゃんはママの母乳からヨウ素を摂ることが考えられます。
離乳食で使うときは薄めて使うようにしましょう。
離乳食に使う昆布だしの量は、大さじ1杯程度までにし、風味づけでおかゆや料理に使うようにします。
離乳食の進め方についてはこちらの記事も参考にしてください。
離乳食の昆布だし、選び方ポイント
昆布からだしをとる場合
昆布からだしをとる場合は、肉厚の乾燥昆布(真昆布)を選ぶようにします。
離乳食用に少量のだしをとるのではなく、大人の食事用に準備した昆布だしから少量とって使うとよいですね。
市販の昆布だしを使うときは注意
市販の粉末だしを使うのであれば、離乳食用の塩分・化学調味料無添加のものを選ぶようにします。大人用の粉末だしは、化学調味料や塩分、添加物が使用されている場合があり離乳食には味が濃いからです。
昆布だしを取る時間がない場合は、離乳食(ベビー)用の粉末だしを利用するとよいですね。
離乳食の昆布だしのとり方
ゴックン期・離乳初期(生後5〜6ヶ月頃)
昆布だしをとったことがない!というママ・パパのために、基本の昆布だしのとり方をご紹介します。まとめて作ってストックしておくと便利です。
材料
作りやすい分量:2.5カップ分
- 昆布 約6×3㎝ 1枚
- 水 3カップ(600ml) ※1カップ=200mlの計量カップ
作り方
- 昆布の表面の汚れを、乾いた布かキッチンペーパーで拭き取り、切り目を入れる。
- 鍋に分量の水と昆布を入れ、約30分つけておく。
- 鍋を弱火にかけ、沸騰直前に昆布を取り出し、一煮立ちさせて火を止める。
詳しくは動画で!離乳食の昆布だしのとり方をチェックしよう
管理栄養士からのワンポイントアドバイス
水出しの昆布だしを使用するときは必ず加熱をして使用しましょう。
昆布だしを水出しで用意するときは1Lあたり、20〜30gの昆布をいれて冬場なら3時間以上、夏場なら2時間ほどおきましょう。
昆布にはヨウ素が含まれています。ヨウ素には摂取量の上限があり注意が必要です。
大人のだしを薄めて使用しますが、ヨウ素を摂りすぎないように、毎日与えるのは避けましょう。
食物アレルギーについて
昆布だしの原材料である昆布は、まれに食物アレルギーを発症する危険性があります。
そのため、初めて与える際は少量から始めましょう。
また、万が一食物アレルギーを起こした場合すぐに病院へ行けるよう、平日の午前中など医療機関を受診できる時間に与えるようにしましょう。
離乳食の昆布だしは冷凍保存できる?
冷凍保存OK
昆布だしはまとめて作って、冷凍保存しておくと便利です。冷凍保存した昆布だしは1週間以内を目安に使いきるようにしましょう。
昆布だしは必ず使う直前に、電子レンジまたは小鍋などで再加熱するようにします。自然解凍した昆布だしを使わないようにしましょう。
(期間の記載は目安となっています。環境によって保存期間に差が出る場合があります。 匂い、味、色、食感が少しでもおかしいと感じたら廃棄してください。)
離乳食の昆布だし、冷蔵の場合はどれくらい持つ?
当日中に使いきる
冷蔵保存した昆布だしは、当日中に食べきるようにします。冷凍保存した昆布だしと同じように、与える前に電子レンジまたは小鍋などで再加熱します。
昆布だしを活用! 離乳食のおすすめレシピ
離乳食の昆布だしとうどん
うどんは、ゴックン期・離乳初期(生後5〜6ヶ月頃)から食べられます。
ゆでうどんを細かく刻んで、とろとろになるまで昆布だしで煮込みます。水分がなくなりそうな場合は水を足してください。
初めて食べるときは、1日小さじ1杯からはじめましょう。
離乳食の昆布だしと豆腐
豆腐もゴックン期・離乳初期(生後5〜6ヶ月頃)から与えることができます。
豆腐は口当たりのよい絹ごし豆腐を使用しましょう。月齢が進んでも、離乳食では豆腐も必ず火を通して与えるようにします。
離乳食の昆布だしと野菜
ゴックン期・離乳初期(生後5〜6ヶ月頃)では、にんじんやたまねぎ、さつまいもなどが調理しやすく適しています。アクがなく繊維の少ない野菜なら、基本はOKです。
大人用の料理を味付けする前に取り分けると、負担が少なく離乳食を用意できます。
上記の野菜以外に、かぼちゃ、大根、かぶなどくせのない野菜も調理しやすくて離乳食向きです。少しずつさまざまな食材を経験させてあげましょう。
離乳食の昆布だしで親子丼
ここで紹介する親子丼は、カミカミ期・離乳後期(生後9〜11ヶ月頃)からのレシピです。レンジで簡単に作れて、卵がふわふわの親子丼です。
卵はしっかり火を通すようにしましょう。
- 昆布だしはゴックン期・離乳初期(生後5〜6ヶ月頃)からOK
- 昆布はヨウ素の摂取量の上限があるので薄めて使用します
- 過剰にとりすぎないように昆布だしだけを毎日与えるのは避けましょう
保存についての注意事項
- 作ったものは常温のまま長時間放置しないでください。雑菌が増える原因になります。
- 清潔な保存容器を使用してください。
- 解凍したものの再冷凍はしないでください。雑菌が増える原因になります。
アレルギーについての注意点
レシピには、特定のアレルギー体質を持つ場合にアレルギー反応を引き起こすおそれのある食品を含む場合がございます。
また、初めて召し上がるお子さまには注意が必要ですので、様子を見ながら少量から食べさせてください。
[特定原材料] えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生
[特定原材料に準ずるもの] アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、マカダミアナッツ
「料理を楽しむにあたって」の「乳幼児への食事提供について」もご参考ください。
写真提供:ゲッティイメージズ
※当ページクレジット情報のない写真該当