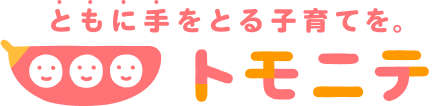【管理栄養士監修】離乳食の醤油|いつから?うす味でもおいしくするコツは?
今回の記事では離乳食の味つけを始めるタイミングや、うす味でもおいしく仕上げるコツ、醤油などの調味料を使う場合の量の目安などを紹介します。
今回の記事では離乳食の味つけを始めるタイミングや、うす味でもおいしく仕上げるコツ、醤油などの調味料を使う場合の量の目安などを紹介します。
[PR]おすすめはこちら!

ファーストスプーン宅配離乳食
2,250円
離乳食では醤油などの調味料はできるだけ控える
離乳食では、醤油などの調味料はできるだけ控えます。
醤油に含まれる塩分(ナトリウム)は、母乳や育児用ミルク、離乳食の食材自体にも含まれているので、あえて離乳食に醤油や塩、みそなどの調味料で味つけをする必要はありません。
離乳食の時期は、素材本来の味を知ることで味覚を育てていきましょう。
離乳食の時期に素材本来の味から甘みやうま味などを覚えることで、食事の味つけがうす味でもおいしく感じられるように味覚が育ち、将来子どもが成長したときに、塩分の取りすぎが原因の1つである高血圧症などの生活習慣病を予防することにもつながります。
離乳食を開始したら、まずは醤油などの調味料は使わずに離乳食を進めていきましょう。
離乳食の味つけを始めるタイミングは、離乳食を食べたがらない場合の対処法として
前述のとおり、離乳食を開始したら、まずは味つけをしないで離乳食を進めていきます。
離乳食を進めていくと、子どもが離乳食を食べたがらなくなることもあります。
この場合、まずは離乳食の固さが子どもに合っているか、授乳や食事の間隔が短すぎてお腹が空かない状況になっていないかなどを振り返ってみましょう。
もし離乳食の固さが子どもに合っていて、授乳の間隔が短すぎることもないのに離乳食を食べたがらない場合は、離乳食に味をつけることでよく食べるようになることもあるため、食材自体に塩気があるしらす干しなどの食材を取り入れたり、うす味での味つけを試してみるのもいいでしょう。
食材自体にうまみの多い食材や塩気のある食材を活用
離乳食に醤油や塩などで味つけを開始する前に、だし汁やかつお節などのうまみのある食材を使うと、うす味でもおいしく感じられます。
また、しらす干し、チーズなどの食材自体にうまみと塩気のある食材を取り入れてみてもいいでしょう。
これらの工夫は、離乳食や大人の食事にも活用できます。
食パンやうどんなど、製造時に塩が加えられている食材もありますので、食材の塩分を活かします。
食材自体に塩気のある食材・製造時に塩が加えられている食材
離乳初期(生後5〜6ヶ月頃)からOK
- しらす干し
- 昆布だし
- かつおだし
- 食パン
- うどん
など
離乳中期(生後7〜8ヶ月頃)からOK
- カッテージチーズ
- かつお節
- ツナ水煮缶(食塩不使用のもの)
- のり(青のり、焼きのり、あおさ)
- わかめ
- とろろ昆布
など
離乳後期(生後9〜11ヶ月頃)からOK
- 桜えび
- 粉チーズ、プロセスチーズ
など
うまみの多い食材
離乳初期(生後5〜6ヶ月頃)からOK
- しらす干し
- 昆布だし
- かつおだし
など
離乳中期(生後7〜8ヶ月頃)からOK
- カッテージチーズ
- かつお節
- ツナ水煮缶(食塩不使用のもの)
- ささみなど離乳中期(生後7〜8ヶ月頃)か与えられる肉類・魚類
など
離乳後期(生後9〜11ヶ月頃)からOK
- 桜えび
- 粉チーズ、プロセスチーズ
- 牛赤身肉など離乳後期(生後9〜11ヶ月頃)から与えられる肉類・魚類
など
味つけをする場合の塩分量の目安は?
子どもが離乳食を食べたがらない場合の対処法として、うす味での味つけを開始する場合は、塩分濃度が0.5%以下になるように味つけをします(WHO/FAO勧告より)。
日本ベビーフード協議会では、ベビーフードの味つけが、1歳までが対象の商品は塩分濃度約0.5%以下、1歳〜1歳6ヶ月までが対象の商品は塩分濃度約0.7%以下になるように自主規格を設けています。
塩分濃度0.5%というのは、もし濃口醤油だけを使って味つけをする場合、100gの料理に対して約4g(小さじ約2/3)の塩を使うことになります。
これだけ聞くと離乳食100gあたりの味つけに醤油を4g使っていいと思ってしまうかもしれませんが、味つけ用の塩以外にも、野菜や肉、魚、卵などそのままの食材自体にも少量の塩分(ナトリウム)が含まれています。
また、食パンやうどん、チーズなどの、製造時に塩が加えられている食品を離乳食に使うこともあるので、味つけで塩を加えていなくても塩分をとっていることがあります。
そのため、離乳食100gあたりの味つけに醤油を4gを使ってしまうと、離乳食全体の塩分濃度は0.5%より多くなることがほとんどです。
離乳食の味つけを開始するのは、離乳中期(生後7〜8ヶ月頃)以降、離乳食を食べたがらなくなった頃を目安に、1食あたり、醤油やみその場合は1g(小さじ1/6)以下から使い、塩の場合は少々よりも少ないごく少量(0.05g程度)から使い、ほんの風味づけ程度のうす味にとどめましょう。
なお、味付けをしなくても離乳食を食べる場合には、調味料を加えずに、素材の味だけの離乳食を続けて構いません。
醤油や味噌、ケチャップ、マヨネーズなどの塩味がある調味料は、塩と同じ重量を与えた場合は塩より塩分量が少なく、風味なども加えられて角のまるい塩味がつけられます。離乳食に味つけをする場合は月齢に合わせてこれらの調味料も活用してみてもいいですね。
醤油に含まれる塩分はどれくらい?
醤油には、濃口醤油であれば小さじ1杯で約0.9g、薄口醤油であれば小さじ1杯で約1.0gの塩分が含まれます。
いずれの場合も「小さじ1杯で約1.0gの塩分が含まれている」と覚えておくと便利です。
醤油を使った離乳食レシピ
醤油を使った離乳食レシピ動画を紹介します。
子どもに合わせて、レシピの醤油の量より量を減らしたり、味付けの調味料は無しで作ってもOKです。
ぜひ参考にしてみてくださいね!
野菜もお肉もこれ1つで! カミカミ期の1食献立例(生後9〜11ヶ月頃から)
これ1つで野菜と肉が一緒に食べられる野菜あんかけ丼を紹介しています。
冷凍保存もできるのでストックしておくと便利です。
ひき肉だから食べやすい! 子どももよろこぶ肉じゃが(生後9〜11ヶ月頃から)
ひき肉を使っているので離乳食でも肉が食べやすい肉じゃがのレシピです。
調理の途中で材料を取り分けて、大人の分も一緒に作ることができます。
食べたいときにすぐに作れる レンジで親子丼(生後9〜11ヶ月頃から)
電子レンジを使って、簡単に親子丼が作れるレシピです。時間がないときでもすぐに作れますよ。
こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
参考
・五十嵐隆(監修)、『授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版)実践の手引き』、公益財団法人 母子衛生研究会、2020年
・『日本人の食事摂取基準(2020年版)』 (厚生労働省)
・『日本食品標準成分表2020年版(八訂)』 (文部科学省)
写真提供:ゲッティイメージズ
※当ページクレジット情報のない写真該当